美の壺「魅惑のきらめき 切子(きりこ)」の再放送は?薩摩切子職人の開発秘話も紹介!
目次
BSプレミアム「美の壺」
「美の壺」は、暮らしの中に隠れたさまざまな美[美しいもの]を紹介する新感覚の美術番組です。普段使いの器から家具、着物、料理、建築に至るまで、衣食住、人の暮らしを彩ってきた美のアイテムを取り上げていきます。
古今東西の美しいものの魅力を、洒落たジャズとともに、贅沢かつ知的に伝えます。日本人ならではの暮らしの知恵やこだわりは、見る者を豊かな気持ちにしてくれるはずです。
番組ではそれぞれのアイテムの選び方・鑑賞法を、いくつかの「ツボ」に絞ってわかりやすく解説してくれます。目指すは実際に使える「美術の鑑賞マニュアル」なんだとか・・・。この番組で紹介したツボを覚えていただけば、骨董店や美術館でも、ひとかどの「通」として振る舞うことができるかも・・・。 って言うのは、ちょっと言い過ぎかもしれませんが・・・。でも、美しいものを見ているだけでも、心が洗われるような感じがするのは私だけでしょうか!?
出演者 草刈正雄
ナレーション 木村多江
題字 紫舟
「美の壺」の再放送は?
「美の壺」は、BSプレミアム毎週金曜日午後7時30分~放送します。また、再放送は毎週金曜日午前6時~です。さらに、過去に反響の大きかった番組のアンコール放送「美の壺・選」は、Eテレ毎週日曜日午後11時~放送しています。
音楽
NHK 美の壺 ブルーノート・コレクション
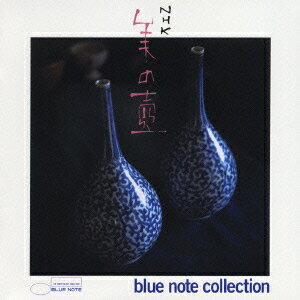
NHK 美の壺 ブルーノート・コレクション [ (オムニバス) ]
伝統工芸の美を伝えるNHKの番組『美の壺』。本作ではオープニング・ナンバーの「モーニン」から、番組内で使われたスタンダード曲を収録。
美の壺「魅惑のきらめき 切子(きりこ)」
<File440>
放送 2018年3月16日(金)午後7時30分~8時[BSプレミアム]
放送前の予告
ガラス表面にカットを入れる工芸、「切子(きりこ)」。その文様には、子孫繁栄、円満、魔よけなど、それぞれ意味が込められています。まるで宝石のような輝きを生み出すカットの技は100分の1mmの精度が求められる超絶技巧だったんです!
前代未聞といわれた「黒い切子(きりこ)」に成功した薩摩切子職人の開発秘話もご紹介します!驚きは、和の料理人とコラボした独創的な切子(きりこ)です。切子(きりこ)の新たな魅力が発見できる30分です!
【出演】草刈正雄,【語り】木村多江
薩摩切子とは?
「薩摩切子」は、江戸末期に薩摩藩で造られた切子ガラスです。鉛を24~25%含むクリスタルガラスを使用し、無色のガラスの表面に色ガラスを1~2ミリ程度溶着させます。その色被せガラスにカットを施し、磨きあげた製品を「薩摩切子」と言います。薩摩切子は、被せたガラスに厚みがありますが色味が淡い為、クリアガラスから色ガラスの間にできるグラデーション「ぼかし」が特徴でです。現代では、シャープな仕上がりが特徴の薩摩黒切子や、薩摩ブラウンなど先人が挑戦し続けてたように、技術だけでなく本質の継承を心掛けて、新しい薩摩切子も制作しています。
「伝匠 薩摩切子」幕末から明治初期に栄えた薩摩切子を、先人より伝えられた意匠と技術を受け継いだ匠が、現代の技術と発想を以って蘇らせました。当時から輝き続ける薩摩切子の魅力を後世へと伝えたい、という想いのもと「伝匠 薩摩切子」と称して温故知新の精神で創られた作品です。薩摩切子の魅力の一つに色ガラスの豊富なバリエーションがあげられます。幕末の匠によって創りだされた8色に加え、現代の匠によって生み出された黒。色のバリエーションには先人より伝わる現代匠の魂と情熱が込められています。

薩摩切子 黒切子 盃 薩摩びーどろ工芸 送料無料 還暦祝 結婚祝 退職祝 記念品 日本酒 父の日 伝統工芸・陶器の和遊感

薩摩切子 黒切子オールド 薩摩びーどろ工芸 送料無料 還暦祝 結婚祝 退職祝 記念品 日本酒 父の日 伝統工芸・陶器の和遊感

薩摩切子 黒切子 薩摩びーどろ工芸 ワイングラス 送料無料 還暦祝 結婚祝 退職祝 記念品 日本酒
放送後のポイント解説
切子の発祥「江戸切子」
切子って言うと夏のものとか、冷たい料理を入れるものっていうイメージがありますが、最近は熱いコーヒーを入れる切子のカップなど、先入観を打ち破るようにさまざまなシチュエーションで切子が使われています。
切子は、約180年前に江戸の下町で作られ始めました。直線や曲線の切り込みを組み合わせて作られる模様には一つ一つ意味があります。魚子(ななこ)模様は子孫繁栄、籠目(かごめ)模様は幸せを掴めるようにという思いや魔除けの意味があるそうです。
江戸切子の特徴は、屈折率が高いため虹色の煌きを放ちます。当時は、コップ、お皿、重箱などが切子で作られていました。最近では、ひな人形やひな道具というちょっと変わった切子も登場しています。特に、ひな道具は1/10サイズのミニチュアです。細かいカットが精緻に施されています。
幕末に薩摩で生まれた切子「薩摩切子」
幕末に薩摩藩主・島津斉彬が西洋の技術を取り入れて普及させたのが「薩摩切子」です。江戸切子とは違うその特徴は、透明なガラスの外側に色ガラスを隙間なく重ね合わせて作る厚みのある切子なんです。そして、もう一つの特徴は、「ぼかし」と言われるゆるやかなカットから生まれるグラデーションです。薩摩切子は、色ガラスと巧みなカット技法の相乗効果で生まれる「ぼかし」が最大の魅力なんです。
黒切子の登場
「黒の衝撃」とも言われた黒い切子が薩摩切子から登場しました。そもそも、黒は光を通さないため、これまでの常識を覆す衝撃の切子だったわけです。鹿児島は黒豚などに代表される「黒」文化が育まれてきた地ですから、黒切子を生み出したいという気持が強かったようです。しかし、この「黒」を作り出すことに大変苦労したそうです。それでも、さまざまな金属の配合に2年以上もの開発期間をかけ試行錯誤の末、黒色のガラスを生み出したそうです。しかし、黒いガラスは光を通さないため、作業をすることができません。そこで、明り取りの窓を作って作業をしたんだそうです。こうして、いくつもの困難を乗り越えて生まれた「黒切子」は大きな反響を呼びました。
料理人と切子職人のコラボレーション
江戸切子職人の堀口さんが作る切子には、使う人の視点に立った工夫が施されています。ぐい吞みは、水を入れると光の屈折が加わり、飲む人の視線から光輝く宝石のように見えるのです。
そんな堀口さんが切子を愛する料理人と一緒に作り出した切子は、雪の「かまくら」をイメージしたドーム型の器です。その切子の器を使った料理は「松葉カニの甲羅盛り」でした。カットのレンズ効果でカニを万華鏡のように映し出してくれます。



